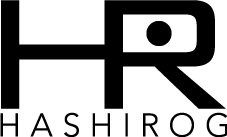先週末は久しぶりに楽しいお酒を飲むことができ、ここ数ヶ月間蓄積していたストレスを少なからず発散したように思います。
ところで、総務省が発表した日本国内blogに関する調査で、公開されているblog総数1,690万サイトのうちアクティブなblog(更新頻度が1カ月に1回以上)は約300万サイト(18%程度)に過ぎない事が明らかになりました。
数字的に、アクティブなblogは2004~2005年にかけて急増し、その後はほぼ横ばいの状況が続いています。
現段階で1カ月間に開設されているblog数は40~50万サイトで、2001年1月以降に開設されたblogサイトの累計は約2240万サイトだそうです(毎月の新規書き込み記事数は2004~2005年にかけて急増したが、その後は減少傾向)。
また、国内blog記事総数は13億5000万件で、データ総量が約42TB(テキストは12TB)となり、その量が記事数や画像・動画等の増加に合わせ毎月1.6TB程度ずつ増えているそうです。
ブログの開設動機としては私もそうですが、自己表現がトップで以下コミュニニケーション・情報発信・データアーカイブ(DB)・副業・ボランティアの順だとか。
以前は日課だったblogも今は週休2日になって少々不安もあったのですが、アクティブなblogとしての条件は十分だという事がわかりました。
これからblogを開設しようとしているMさんも週1回のペースから始めても良いのかもしれません(笑)。
図書閲覧の新スタイル
帰宅時に車の給油をしてきたのですが、いつものように満タンにしたら、10,000円で足りないんですね。180円/Lとはこういう事なのだと実感しました。
最近、Web図書館が注目を浴びています。千代田区立千代田図書館がそうなのですが、インターネット経由で書籍データを自宅PCにダウンロードして読めるサービスを提供しています。
ユーザーは1年中、いつでも本の貸し出し・返却をPC上で行うことができるため、図書館まで足を運ぶ必要が無いという特徴があります(Web図書館の導入を検討する図書館もでているとか)
昨年11月にWeb図書館を開設した千代田図書館の例をとると、書籍データをネット経由でPCに受信しマウス操作で1ページずつめくるように読むことができるそうです(メモの書き込みや視覚障害者や高齢者に配慮した音声による読み上げ機能も)。
基本的に図書館へ出向くという手間や行動を必要としないため、身体的に不自由な人でも閲覧が可能となるのがメリットです。
書籍のデータベースと電子ブック化で、必要な時に場所を選ばず図書館の本を閲覧できる図書館がますます増えてくるのかもしれません。
IP
最近、サイトリニューアルの仕事に伴いサーバーの奥深さを改めて感じる出来事がありました。
このところ、IPアドレスの在庫枯渇の話がクローズアップされているようです。予想によると、IPv4アドレスが2010年ごろには底をついてしまうとされ、ISP(Internet Service Provider)がインターネットレジストリから新たな IPv4アドレスを手に入れることができなくなるそうです。
当初、約43億のアドレスしか管理できないシステムを作った事に原因があるとも言われていますが、IPv6という次世代IPプロトコルに変わる事でこの問題は解消出来るとされています(問題はIPv4とIPv6の間に互換性が無い事)。
近い将来、IPv6のサイトが増えてくるという事は現時点での私達IPv4ユーザーにとって、少しずつ肩身が狭くなるという予想なのかも知れませんね(笑)。
SWF
このところ、毎日がめまぐるしく過ぎていくようです(忙しい理由が不明瞭ですが)。
ところで、アメリカのAdobe社がFlash使用のWebコンテンツやアプリケーションの検索を容易に行えるようGoogle・Yahoo!と提携したそうです。
この2社はFlashファイルフォーマットを検索インデックスに取り込めるように最適化されたFlash Player技術を提供する事で、今のところ検索エンジンでは見つけられない情報の開示を行います。
従来、検索エンジンはFlashファイルフォーマット内の静的テキストとリンクする事でインデックス化していたが、Flashコンテンツは基本的に状態が変わるため検索インデックスに取り込むのが困難とされていました。
しかし、提携する事でFlash Player用ののリッチインターネットアプリケーション(RIA)やWebコンテンツが今後検索で見つかりやすくなるという訳です(特にFlashコンテンツに変更を加える必要が無い)。
既にGoogleはFlash Player技術を検索エンジンに取り入れ、Flashコンテンツが検索可能になっているそうです。Yahoo!のSWF検索対応も含め、Webコンテンツづくりも少しずつ変わってくるのかもしれません。